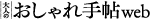年齢を重ねるにつれてどうしても気になる、肌のたるみやむくみ。
いろんなケア方法がありますが、体の内側からのケアとして「春の土用」の薬膳を実践してみませんか?
明日からはじまる「土用」の季節は、たるみやむくみを改善するのに最適な季節。
たるみやむくみのケアにぴったりな食材の組み合わせと、薬膳メニュー例をご紹介します。
季節の変わり目「土用」は、脾(ひ=胃腸)の働きがさかんになる季節

明日4月17日から5月4日までは「春の土用」となります。
「土用」とは四季のはじまりの日である立春、立夏、立秋、立冬それぞれの直前約18日間のことで、夏だけではなく、年に4回訪れる季節の変わり目の期間。今回やってくる春の土用は立夏(5月5日)前の18日間で、春から夏への変わり目となります。
土用については「50代のこよみ養生 Vol.11」でも詳しくお伝えしましたが、ポイントとなるのは「脾(ひ)の働きがさかんになる季節」ということ。
脾とは体のしくみを5つに分類した東洋医学の考え方である「五臓」のひとつで、胃腸の働きに相当しますが、消化機能のみにとどまらない広い意味での胃腸の働きが含まれています。そのひとつがたるみを防ぐ“上昇力”です。
脾には食べたものを栄養に変えるだけでなく、その栄養を上昇させて心肺や頭部へと運ぶ働きもあります。この脾の“上昇力”は、内臓が下垂しないように固定するなど、体のあらゆる部位が重力に負けないよう引き上げる力でもあり、肌のたるみを防ぐ力にもなっています。
さらに脾には、むくみを防ぐ“排水力”もあります。食べたものに余分な水分が含まれている場合、脾はその水分をほかの臓に送って、汗や尿として排出します。この脾の“排水力”が低下すると余分な水分が体内にたまってしまい、むくみや肥満の原因となってしまうのです。
脾の働きがさかんになる土用は、こうした脾の“上昇力”や“排水力”もさかんになる季節。たるみやむくみを改善する絶好のチャンスでもあるわけです。
(広告の後にも続きます)
たるみやむくみの原因は、体の中に生まれる“ぬかるみ”

春の土用の養生には、脾のケアに加えてもうひとつ押さえるべき点があります。
それは、肝(かん)も一緒に養生するということです。
五臓のひとつである肝の主な働きは、気(き=エネルギー)を上向きにめぐらせること。これは例えるなら、上に伸びる「木」のような働きといえます。
そして、飲食物を分解して栄養を作る脾の働きは、落ち葉などを分解して養分を作る「土」のようなもの。
つまり肝と脾は、木と土のように密接な関係にあるのです。
春になると木はどんどん上に伸びて成長し、その栄養源として土から養分や水分をどんどん吸収していきますよね。
同じように人間の体も、春になると肝が脾からどんどん栄養を吸収し、それを糧に気をどんどん上向きにめぐらせて、心身を活動的な状態に導いていきます。
しかし、木にストレスが加わるとどうなるでしょうか。例えば木が日当たりの悪い環境に置かれると、成長が止まり、枝葉の元気がなくなってしまいます。すると木が土から養分や水分を吸収する量も少なくなるため、土の水はけが悪くなって“ぬかるんだ森”となってしまうでしょう。
春の土用は、まさにこの“ぬかるんだ森”のような状態が体の中に発生しやすいとき。
春のストレスを受けると肝の働きは低下し、気のめぐりが悪くなるために脾の働きも低下してしまうため、余分な水分や未消化物などがたまって“ぬかるみ”のような状態になりやすいのです。すると、たるみやむくみが起こりやすくなるほか、次のような不調も現れやすくなります。
・べっとりした便が出る
・排便してもすっきりしない
・おなかやわきが張って痛む
・食欲が出ない
・おならがよく出る
・下痢したり便秘したりする
・ため息がよく出る
・うつになる
“ぬかるんだ森”を改善するためには、木が上に伸びるように成長するのを助け、土の水はけをよくして養分を作る力を高めなければなりません。
同じように私たちの体も、肝の働きを助けて気のめぐりを促進し、脾の働きを整えることが、“ぬかるみ”を改善してたるみやむくみなどをやわらげることにつながるのです。