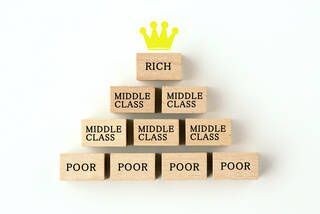東日本大震災から14年の月日が経った。
2011年の5月に訪れた時は、瓦礫がどっさりと山積み。異様な匂いが街に充満していた。その瓦礫のひとつをも動かせないワタシ(中村修治)に出来ることなどない。茫然とするしかなかった。
2014年の6月に訪れた時は、街が動き出していた。
復興の予算がインフラを整え直し、街に日常が戻りつつあった。
2025年2月に、再び気仙沼を訪れた。そのレポートをここに公開。読者のみなさんと一緒に『創造的復興』とは、何だったのか!?を一緒に考えてみたい。
高ーい防護壁から見えるものは!?
大津波の被害を受けた海沿いの街には、巨大防波堤となる防護壁が張り巡らされている。街から望む海の景観は、5~7mの壁に遮られていた。気仙沼市の震災後のテーマは「海と共に生きる」。”共に生きる”とはこういうことなのか!?なんとも皮肉な光景だ。

防護壁
現地の方の話を聞くと、どうやら政府主導の復興策は、土木工事がセット。遠くに見えている壮大な三陸道も然り。街の一刻も早い復興を望むなら、この巨大防波堤を拒むことはできないという実情があったらしい。
東北の海と暮らしてきた人達は、そもそも震災の時って、自然の脅威って、人間の力ではどうしようもないくらい凄まじいな…って実感したので、防潮堤全般について、作ってもしょーがねーよ、とは何処かで感じていた。でも、街の復興が第一なら、巨大防波堤も承諾するしかない。
では、あの取ってつけたような覗き窓は!?という問いに、気仙沼に住む若者が答えてくれた。

覗き窓
「当然『巨大な壁で海が見えないこと』がむしろ危険ではないか?みたいな議論の中で生まれたのが覗き窓付防潮堤。少なくない人達が『そーゆーことじゃねーよ!』とずっこけつつ、住民参加とか、住民の声を聞きました的案件の酷さに度肝を抜かれたというか、逆に腰砕けというか…あれって、あきらかに『行政側の善意』なんですよ(笑)」
「防潮堤の利権もマクロで考えたら、元請け・下請けの違いとかも含めて利権なんでしょーけど、 明らかにこの14年、『公共事業』として機能しました。でも10年も経つとダンプカーとか目に見えて減って。借り上げだったアパートはガラガラとか、一気に地域経済ピンチです(笑)いや~難しい」
復興というお題目は、最高の善意だ。ヒトは悪いことより、良いことの方に積極的に加担する。根っから悪い人ではない者が集まって、根が深く絡み合った巨大な悪が出来上がっていく。善意という後ろ盾に、人間はエスカレートする。悪事は、善意を背負って千里を走り、迷走するのである。利権で固められた巨大防波堤の覗き窓から見えているのは、さまよえる善意だ。
(広告の後にも続きます)
やることはやったけど…。
気仙沼という街に、日常は戻っている。電気は灯る。水も蛇口を捻れば出る。下水道の心配もない。しかし、仮設の店舗は、そのまま営業中。各店舗の落ち着く場所は、まだ、定まっていない。仮設のままである。

仮説の店舗
復興のシンボルとなるような小規模な商店&飲食街も出来上がっている。その名も「Kesennuma Amway House」。資本に余裕がある民間企業が支援を行い、施設の冠になっている。

Kesennuma Amway House
夜になると気仙沼港に隣接する復興予算が注ぎ込まれた商業施設には、煌々とイルミネーションが灯される。しかし、お客さまがいない。静か過ぎる。

夜の商業施設
創造的復興の名のもとに“やることはやった”結果がこれである。みんなで話し合い、予算を分け合い、ひとつひとつカタチにしてきた。でも、戻ったのは生きているという日常であって、大きな夢に向かっているという前向きな日常ではない。若い人達を街に留めることができる創造性は、ここにない。
誰かに文句を言える筋合いはない。受け止めるしかない。やることはやったと自分達に言い聞かせるような静けさだけが聞こえてきた。