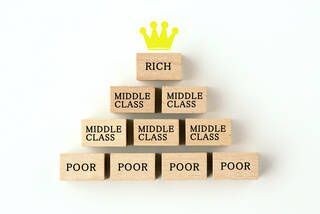【介護者】介護離職を防ぐための支援制度が強化
今や要支援・要介護認定者数はおよそ700万人。公的介護保険制度がスタートした2000(平成12)年度の認定者数約256万人に比べると3倍近く増加しています。65歳以上のおよそ5人に1人が支援や介護が必要という状況です。
参考:厚生労働省「令和4年度 介護保険事業状況報告(年報)のポイント」
一方で家族の形態も変化しており、3世代が同居しているというケースは非常に珍しくなりました。核家族化が進む中で、親や祖父母の介護のために頻繁に実家に帰らなければならず、仕事を辞めなければならないという人もいます。いわゆる介護離職です。
介護離職者は毎年10万人に上り、特に50~64歳で介護離職をする人が非常に多い現状にあります。この年齢層は、親が70代や80代を迎え、介護の必要性が高まる時期と重なります。
50歳といえば会社では大きな仕事の責任者となったり、若手の育成をしたりするなど重要なポストに就く人も多いでしょう。当然会社の期待も大きいところですが、そんなタイミングで介護離職となれば本人はもちろん会社にとっても損失です。なんとか離職せず仕事と介護が両立できるように、介護休暇を取得できる条件が緩和されることや介護のためのテレワーク導入など、今回の改正がしっかり労働者に周知される必要があります。
(広告の後にも続きます)
育児休業の取得状況の公表義務が300人超の企業にも拡大
改正の全体ポイントのに「育児休業取得状況の公表」とあります。これまで従業員数1000人超の企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が義務づけられていましたが、改正後は300人超の企業に適用が拡大されます。
これによって、より多くの企業が育児休業に対して積極的な取り組みを行うことが期待されます。中には、公表義務の有無に関わらず既に会社独自の制度を設けて男性が積極的に育児休業を取りやすい環境整備をしている企業もあります。こういった企業の取り組み状況の公表は、働く側が勤務先を選ぶ際のひとつの要因となりえます。
参考:厚生労働省「2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が 従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます」