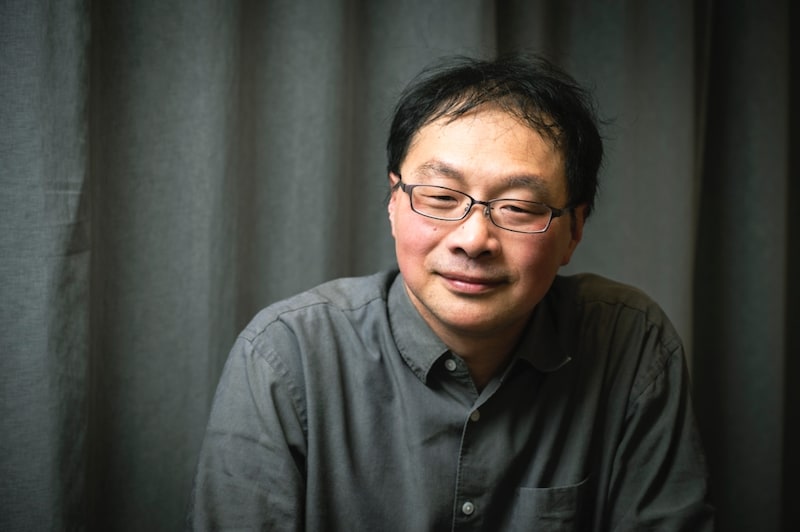裁判に勝つか負けるかではなく、どんな生き方を選ぶのか
池ノ辺 この作品は“恋愛裁判”というタイトルがあり、実際の裁判もニュースになって、もうちょっと丁々発止の裁判の感じなのかと思ったら、そうではなくて、どちらかといえばすごく静かに始まって静かに終わりましたね。
深田 この作品には二つの側面があると思っています。一つはいわゆる“裁判映画”です。おっしゃるように、そもそもが裁判のニュースからこの企画がスタートしました。ただ、その時の自分も裁判の映画というのは作ったことがなくて、僕のイメージの中ではジョン・グリシャム原作の映画作品のような法廷劇もの、あるいは日本の法廷バトルゲーム「逆転裁判」みたいなものをうっすらとイメージしていました。それでいろいろ取材してみたら、日本の民事裁判は地味すぎたんです (笑)。

池ノ辺 たしかに、地味なイメージはありますね。監督は、裁判に立ち会ったり傍聴などもされたんですか。
深田 裁判の取材には行きましたし、あとはこの映画の取材とは関係なく、知り合いの関係する裁判の手伝いなどもしていましたから、そこで見えてくるものもありました。もちろん映画の取材の過程で弁護士の方にお話を伺ったり、法律監修にも入ってもらっています。映画の中では最大限に見栄えのあるところをピックアップしたんですが、本当にあれが限界でした。そこで嘘をついてもう少し派手な法廷劇のかたちにするという手もあったかもしれませんが、この題材でそこまでの虚飾はどうかと思ったのでやめました。
これは脚本を書きながら思ったのですが、もう一つの側面から考えた時、これをいわゆるジャンル化された法廷劇にしてしまっていいのか? ということです。つまり、法廷劇にすると、結局、結論は勝つか負けるかしか無くなってしまう。でも、この、裁判を起こされた山岡真衣というアイドルの姿を描こうとした時に、本当に大事なのは勝つか負けるかじゃなくて、彼女が自分自身の意思で何かを選択することそれ自体だと思ったんです。そうなると、勝つか負けるかというのは、実はこの作品の主題ではないと気がついたのです。もちろん、裁判というかたちを通して描いてはいるけれど、彼女自身がその法廷の場に立たされて、迷い続けているという姿の方が大事だと思って、結果的にこの映画のかたちになりました。だから皆さんが「逆転裁判」とかアメリカの法廷劇みたいなものを期待されてると、あれ? っと思うかもしれませんね。
池ノ辺 確かに、一瞬、そう思ったんですけど、逆に、今までの監督の作品と重ね合わせて考えると、監督らしい作品だなと思いました。山岡真衣がそこで悩んで迷っている。すごくリアルなところで一人の女性の生き様を淡々と語っていて、観る私たちも同時に考えさせられる。そこを見事に表現した演出だったと思いました。
深田 ありがとうございます。




メッセージを押し付けるのではなく、観る人の考えを映画によって炙り出せたら
池ノ辺 監督は今までさまざまな国際映画祭に行かれていますけど、この作品も、カンヌ国際映画祭の「カンヌ・プレミア」部門に正式出品されたほか、世界のさまざまな映画祭で上映されてますよね。
深田 今回もカンヌを皮切りにいくつかの国際映画祭に出品していて、その中で自分が立ち会ったのは、釜山と平遥 (ピンヤオ)、そしてバンコクの国際映画祭でした。
池ノ辺 海外ではどの様に受け止められましたか。
深田 僕は、この作品に限らず、もともとの自分の作家としての信条で、プロパガンダはしない、自分のメッセージや思想を観客に押し付けるようなことはしない、ただ、映画を観ることによって観る人自身の考え方が炙り出されるようなものにしたい、という思いがあるんです。当然、この作品もその原則に則って作っているので、本当に観る人によっていろいろでした。
フランスでは、ここで登場するような女性のアイドルグループに対して男性ファンが圧倒的に多いことがすごく不思議というか奇異に映っていたようです。とはいってもそもそも欧米の人たちは「日本のアイドル」には愛着がないというか、遠い国の一つの芸能という程度の認識なんです。思い入れがない分、単純な社会問題として、それを批判するかしないか、という文脈に捉えられがちでした。一方韓国などはアイドル文化が日常に根付いていますから、そうなると当事者意識を持って自分ごととして捉えている。だからただ単純に批判すればいいということではないな、というのが共通の認識としてあるようでした。そういう反応の違いは面白かったですね。

池ノ辺 アジア圏では共通の“アイドル”の位置付けがあるんでしょうか。
深田 アジア圏といっても“アイドル”の発祥は日本なんですよね。今は韓国の、いわゆるK-POPの方が勢いがあるような感じですけど。この映画を韓国で上映するにあたって、現地で取材なども受けたんですが、韓国人にとっても“アイドル”の源流は日本にあるという認識だそうです。だから、日本での“アイドル”がどうなっているのかにはすごく関心があるようでした。中国でアイドル文化が登場したのはずいぶん後になってからだそうです。
池ノ辺 日本でアイドルというものが認識されだしたのが、1970年代とか80年代ですよね。
深田 そうですね。そこから現在のAKBとかにつながっていく。あの流れは当時は日本にしかなかったでしょうね。
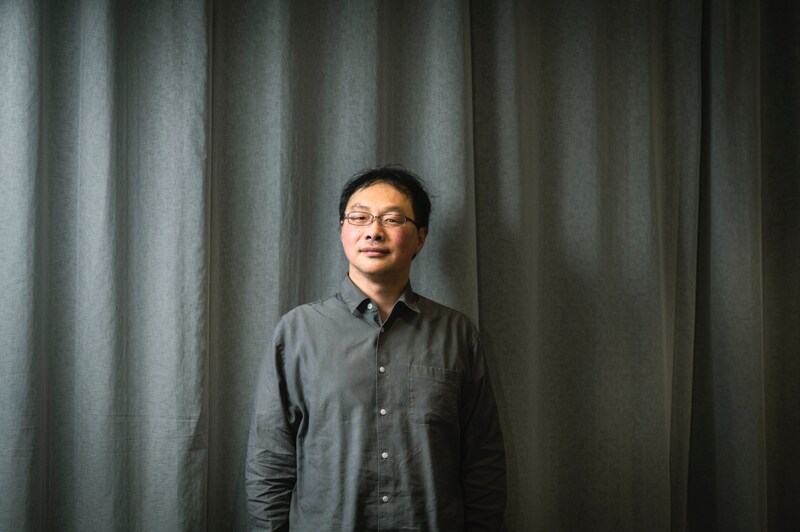
池ノ辺 では、最後の質問になりますが、監督にとって「映画」って何ですか。
深田 自分にとっては、「好きなことの延長線上」にあるものだと思っています。自分が思うに、映画作りをする人って、すごく乱暴に言ってしまうと二つのタイプに分かれるんじゃないかと。一つは「集団創作」、みんなでものを作るということが楽しくて、現場が楽しくて、それで映画作りを続けている人。もう一つは、いわゆる「映画オタク」からスタートして、好きな映画の背中を追っかけて映画業界に入ってくる人。そのどちらかだと思うんです。そして自分は完全に後者です。10代の頃からの映画オタクで、好きな映画に憧れて、「映画って作れるんだ」と映画学校の存在を知って、そこに入って。自主映画からスタートして今でもその延長線上でやっているという意識です。だからいまだに「仕事」という意識が希薄ですね。「趣味は何ですか」と聞かれても結局「映画鑑賞かな」となっちゃうことを思うと、自分にとっての映画は趣味でもあるかもしれないです。
池ノ辺 最高の趣味ですね。
深田 それは本当にありがたいです。やっぱり一緒に作ろうとしてくださっているプロデューサーやスタッフ、キャストの皆さんがいるおかげで、なんとか続けています。
インタビュー / 池ノ辺直子
文・構成 / 佐々木尚絵
撮影 / 岡本英理
監督
2010年『歓待』が東京国際映画祭「日本映画・ある視点」作品賞、2011年プチョン国際ファンタスティック映画祭最優秀アジア映画賞受賞。2013年『ほとりの朔子』が、ナント三大陸映画祭グランプリ&「若い審査員賞」をW受賞。2016年『淵に立つ』がカンヌ映画祭「ある視点」部門審査員賞、2017年芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。2018年仏芸術文化勲章「シュバリエ」受勲。その他の監督作に、『さようなら』(2015)、『よこがお』(2019)、『本気のしるし〈TVドラマ再編集劇場版〉』(2020)、『LOVE LIFE』(2022)、制作中の新作に『ナギダイアリー(仮)』などがある。
作品情報 映画『恋愛裁判』
映画『恋愛裁判』
人気急上昇中のアイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」でセンターを務める山岡真衣は、中学時代の同級生・間山敬と偶然再会し、恋に落ちる。アイドルとして背負う「恋愛禁止」ルールと、抑えきれない自身の感情との間で葛藤する真衣。しかし、ある事件をきっかけに、彼女は衝動的に敬のもとへと駆け寄る。その8カ月後、事態は一変。所属事務所から「恋愛禁止条項違反」で訴えられた真衣は、事務所社長の吉田光一、チーフマネージャーの矢吹早耶らによって、法廷で厳しく追及されることとなる。
企画・監督:深田晃司
出演:齊藤京子、倉悠貴、仲村悠菜、小川未祐、今村美月、桜ひなの、唐田えりか、 津田健次郎
配給:東宝
©2025「恋愛裁判」製作委員会
公開中
公式サイト renai-saiban.toho