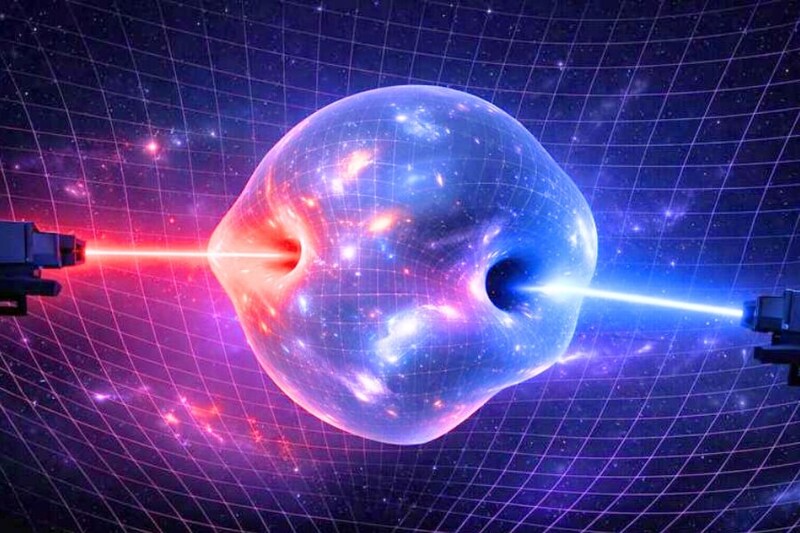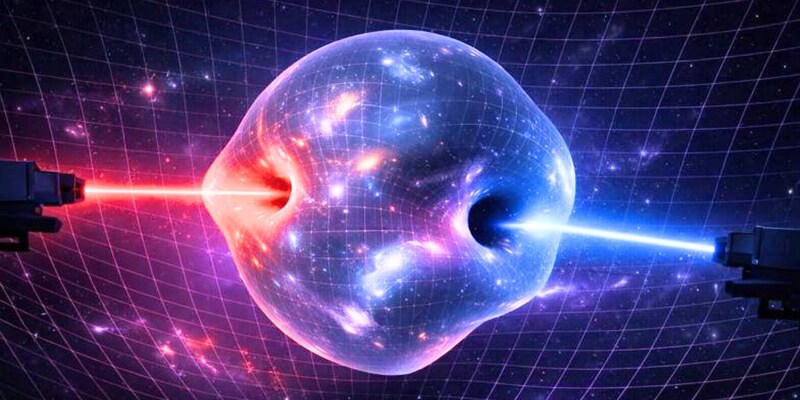
「宇宙の形」を自分の好みでデザインして、机の上の量子デバイスの中にミニチュアとして浮かび上がらせる――そんなSFみたいな発想を、アメリカのスタンフォード大学(Stanford University)で行われた研究によって、理論化され、数値計算で具体的な手順としてまとめることにも成功しました。
研究では「測定する=現実にする」という量子世界の仕組みを巧みに使うことで、粒子どうしの量子もつれのつながり方を、あらかじめ選んだ“宇宙の形”――丸いお皿のような空間や二つの世界を結ぶワームホールのような構造――に合わせて彫刻する方法が示されています。
もしこうした手順が実験装置の上で実現できるようになれば、「観測する」という行為を使って、どこまで自在に時空もどきの世界をデザインできるようになるのでしょうか?
研究内容の詳細は2026年1月28日にプレプリントサーバー『arXiv』で公開されました。
目次
- 量子もつれと時空の形状は関連している
- 観測で時空の形状を彫刻する量子ホログラフィー理論
- 時空=量子情報という見方が意味するもの
量子もつれと時空の形状は関連している
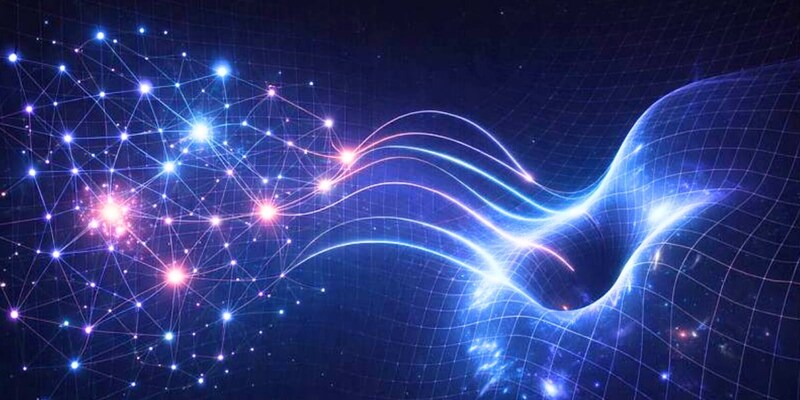
今回の研究のカギになるのが「量子もつれ」と呼ばれるつながりです。
ふつう、コインを二枚投げたら、表か裏かはそれぞれバラバラに決まります。
しかし量子の世界では、二つの粒子が「もつれた状態」になると、どんなに遠く離しても、片方を調べた瞬間に、もう片方の結果もぴたりと決まってしまう、というふしぎな関係が生まれます。
量子コンピューターや量子通信では、この量子もつれを上手に利用しようとする研究がたくさん行われています。
今回の論文では、さらに一歩進めて、「量子もつれそのものが『空間の形』と関係しているのではないか」という、かなり大胆なアイデアに挑戦しています。
では、こんなミクロな量子の世界と、星や銀河が動き回るマクロな宇宙の世界が、どうつながるのでしょうか。
きっかけの一つは、ブラックホール研究から生まれました。
ブラックホールには「エントロピー」、つまり中にどれだけ情報が詰め込まれているかを表す量があると考えられています。
驚くべきことに、そのエントロピーはブラックホールの体積ではなく「表面積」に比例する、という結果が見つかりました。
普通の箱なら、中身の情報量は体積に比例しそうなものなのに、ブラックホールでは表面積が情報量の目安になる、というわけです。
この発見から、「もしかすると、重力を含む本当の宇宙は、三次元や四次元の空間そのものではなく、そのまわりの“壁”に書かれた情報から再現されているのではないか」という大胆な考えが生まれました。
これが「ホログラフィック原理」と呼ばれるアイデアです。
またホログラフィーの世界では、リュウ=タカヤナギ公式と呼ばれるものが、「もつれの量=時空の面積」という対応を与えてくれます。
つまりどれだけ量子情報が絡み合っているかを調べると、裏側の時空がどのように曲がっているかが分かる、というわけです。
こうした関係式のおかげで、「時空の形そのものが、量子もつれから生まれているのではないか」という見方が、一気に現実味を帯びてきました。
そこで今回研究者たちは、「あらかじめ決めた“時空の設計図”に合わせて、内部の粒子を観測することで、その観測操作を利用して“時空もどき”を外側の平面に立ち上げようとした」のです。
果たしてそんな理論は構築可能なのでしょうか?
観測で時空の形状を彫刻する量子ホログラフィー理論

観測によって時空を好きに書き換えられるのか?
研究者たちは手順にしたがってまず「好きな時空の形を先に決めてしまう」ことにしました。
たとえば、境界が円になっていて、中身が双曲空間と呼ばれる独特な曲がり方をしている世界や、二つの宇宙をトンネルでつないだワームホールのような世界です。
それを細かく区切り、点と線からなる「グラフ」として描き直します。
点は小さな量子振動子、線はそれらの間の結びつきを表します。
次に、全ての点にあたる部分に1つの振動子を割り当て、いったんはすべてバラバラな状態から出発します。
そのあとで、ネットワークの線にしたがって全体を一気に「グワッ」と揺らし、内部と境界を含む全体を大きな量子もつれ状態にします。
ここまでは、まだ「中身も外側も全部ごちゃまぜにもつれた大きな世界」にすぎません。
そこで登場するのが「見るから現実になる」という操作です。
「どう測るかをこちらの都合で決めると、最後にどんな状態が“現実”として残るかをかなりの部分までコントロールできる」という、量子力学ならではの性質を、実験プロトコルとして組み立てているわけです。
研究チームはまず、「中身」にいるたくさんの振動子について、どのように“見る”(測る)かを細かく決めました。
具体的には、それぞれの振動子をどのタイミングで、どんな物理量として測るかという手順をあらかじめ設計しておきます。
つまり、「この部分はまとめて測ってしまい、この部分は測らずに境界として残す」といった測り方のルールを人間の側で先に決めておくわけで、このようなあらかじめ人間が設計した恣意的な測定のしかたが、その後に残る世界のかたちを左右することになります。
このプロトコルを実行するとしたら、まず内部の測定を一気に行い、その結果のメモを見ながらレシピどおりに境界の振動子たちに細かい補正を次々とかけていきます。
こうすることで、中身と外側のあいだにあった「見えない糸」(量子もつれ)はいったん測定によって切れてしまいますが、そのときにわかった一見バラバラな数字だけを手がかりにして、外側の状態を最後にきれいにととのえていきます。
すると、最初に「円盤の時空」用のグラフを選んで同じ手順を実行するだけで、表面(境界)を細かく設計しなくても、境界の量子もつれのパターンが自然と円盤形状の時空に対応する状態になっていることが理論的に導き出されました。
同様にワームホール用のグラフを選んでおけば、二つの境界を橋のようにつなぐワームホール幾何に対応した状態が表面(境界)に現れました。
これらの結果は、観測を通じて研究者があらかじめ選んだ時空の特徴を映し出すような量子状態が形成されたことを示します。
コラム:恣意的な観測も現実を作るのか?
「恣意的な観測」と聞くと、「研究者が自分に都合よくデータをいじっているのでは?」と心配になるかもしれません。でも量子力学で言う「恣意的」は少し違っていて、「どんな測り方を選ぶかは人間が自由に決めてよい」という意味です。写真でたとえると、上から撮るか横から撮るか、広角にするかズームにするかはカメラマンが自由に選べますが、一度シャッターを切ったあとの写り方そのものは勝手には変えられませんよね。量子の世界も同じで、「どう測るか」はこちらが決められますが、そこで出てくる具体的な数字は量子力学のルールにしたがってランダムに決まります。この論文でやっているのは、「測り方の設計」と「測ったあとにどう補正するか」というルールをセットで決めておき、どんな数字が出ても、その数字に合わせて外側の量子状態を同じ“型”にそろえる、という仕組みです。ここで“恣意的”なのは「どの物理量をどう測るか」という測定の設計であって、「出た結果を都合よく選び直す」ことではありません。それでも、どの測り方セットを選ぶかによって、最後に残る“現実の状態”(境界の量子もつれの骨組み)が変わるという意味では、「見るから現実になる」「恣意的な観測が時空もどきの形を彫刻している」と言える結果になるのです。
では、その「世界」は本当に選んだ時空の設計図と対応しているのでしょうか。
研究者たちは時空内部を調べることにしました。
まず円盤状の時空の場合、研究者たちは円周上の境界をいくつかの区間に切り分け、それぞれの区間が残りの部分とどれくらい強く量子的につながっているかを調べました。
すると内部に対応する境界の振動子たちの量子もつれの状態は、円盤状の時空に合致するパターンになっていることがわかりました。
ワームホールの例でも、同じようなテストが行われました。
結果、量子もつれのパターンがワームホール幾何で予測される二種類の最短曲線(トンネルをまたぐ経路と、外側を回り込む経路)の振る舞いとよく一致することが分かりました。
言い換えると、「トンネルを通るようなつながり」と「通らないつながり」が状況によって入れ替わる、ワームホールらしいパターンが境界の状態から読み取れたのです。
最後に、「境界のどの部分から、中身のどこまでの情報を復元できるか」という、ホログラフィーならではの問いもテストされています。
中身のある一点にだけつながる“お試し用”の境界点を追加し、いろいろな境界領域を選びながら、その点の情報をどれくらい取り戻せるかを調べていくと、「ここまでは復元できる」「ここから先は難しい」という境目がおおよそ理論どおりの形に現れてきました。
この境目は、リュウ=タカヤナギ公式が教えてくれる「最短曲線で囲まれた領域」とよく重なっており、選んだ設計図どおりの「中身と外側の対応関係」が、実際に境界状態の中に刻み込まれていることを裏付けています。
こうして見てみると、今回の仕事は、「どう測るか」と「そのあとどう手直しするか」をていねいに設計することで、円盤型の時空やワームホール型の時空に対応する“ホログラム世界”を、境界の量子状態としてかなり良い近似として作り出せることを示します。
量子力学の測定はただ結果を乱数として吐き出すだけではなく、「望む現実をえらび取るための道具」としても使えるのだ、ということを、具体的な設計図と数値実験で見せてくれた研究だと言えるでしょう。