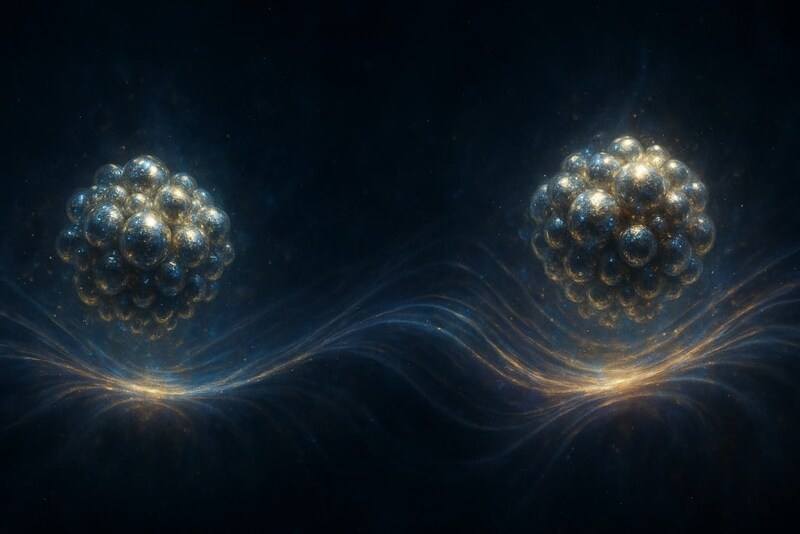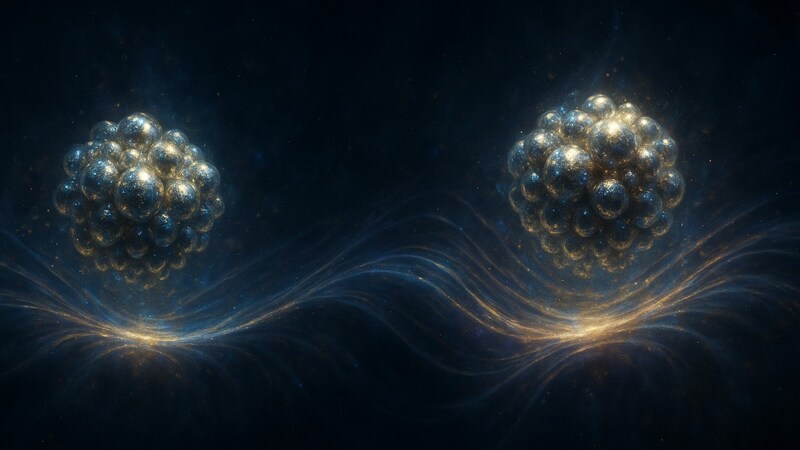
オーストリアのウィーン大学(University of Vienna)で行われた研究によって約7000個もの原子でできたナトリウムのナノ粒子を使った実験で、粒子がまるで波のように同時に複数の経路を進み、その結果として干渉縞(波どうしが重なり合って作る縞模様)を作り出すことを確認しました。
さらに研究チームは、粒子がどれほど大きくても量子のふるまいが維持されるかを示す指標「巨視性(マクロスコピシティ:μ)」を測定しました。
その結果、2019年に発表された分子干渉実験(μ=14.1)を超え、過去最高の巨視性 μ=15.5 を記録しました。
この成果は、量子力学が適用できる物質の大きさの限界を大きく押し広げるものであり、「量子の不思議」は私たちが考えていたよりもずっと身近な世界にまで通用していることを示しています。では、いったいどこまで大きな物体に量子の世界のルールは適用できるのでしょうか?
研究内容の詳細は2025年7月28日に『arXiv』にて発表されました。
目次
- なぜ大きなものは波になれないのか?
- 原子7000個の粒子が描いた量子性
- “猫の壁”突破がもたらす未来
なぜ大きなものは波になれないのか?

私たちの目には、野球ボールや砂粒といった日常的な物体が同時に二つの姿を取ることはありません。
例えばボールを投げれば、常に一つの軌道を描いて飛んでいき、「そこにある」ことが当たり前です。
しかし量子力学の世界では、電子や原子のような微粒子は波と粒の二重人格を持ち、観測するまで複数の経路を同時に進むことが理論的にも実験的にも確認されています。
もしそうなら、「もっと大きな物体でも同じことが起きるのでは?」と考えた人もいるでしょう。1935年、物理学者エルヴィン・シュレーディンガーは、この量子の不思議を揶揄する有名な思考実験「シュレーディンガーの猫」を提案しました。
箱の中に入れた猫の生死が観測するまで重ね合わさって決まらない――そんな風に身近なマクロな存在へ量子論を適用すると途端に奇妙に感じられることを示したのです。
このパラドックスは「本当にそんなことが起こり得るのか?」と私たちに強烈な疑問を投げかけました。
科学者たちはこの謎を解き明かすために、少しずつ「量子の世界」と「私たちの日常の世界」をつなぐ橋を広げようとしてきました。
初期の量子の実験では、電子のような非常に小さい粒子を使って、二つの穴を通したときにできる干渉縞(波と波が重なってできる模様)を観察しました。
その後、徐々に技術が進歩し、原子や大きな分子のような、より大きな対象でも干渉縞が確認されるようになりました。
たとえば、原子一個を使って「半メートル」ほどの距離で波のような状態に広げたり、巨大な分子が波のように振る舞って干渉を起こす実験も実際に成功しています。
最近では、16マイクログラム(1マイクログラムは100万分の1グラム)という、目には見えないけれど原子よりはるかに大きい機械の一部を使って、「シュレーディンガーの猫」と同じような状態を作り出すことに成功しました。
ただ、このときに重ね合わさった距離は約10のマイナス18乗メートル(原子核よりずっと小さい距離)という非常に短いものでした。
これだと、「同時に二つの場所にある」ということを想像するのはやはり難しくなります。
つまり、私たちが直感的に納得できるほどはっきりと量子の「二重人格」を確認するためには、
「もっと大きな物体で、さらに波としての広がり(遠く離れた場所に同時に存在する)が必要だ」ということになります。
では、その壁を打ち破るにはどうすればよいのでしょうか?ポイントの一つは「粒子を可能な限り遅く飛ばすこと」です。
物体の速さを遅くすると、物質波(ド・ブロイ波長)が長くなり、波として干渉しやすくなります。
しかし、物体が重く大きくなるほど物質波は極端に短くなり、通常のやり方では干渉縞を観察することが困難になります。
もう一つの課題は「環境からの影響を徹底的に減らすこと」です。
大きな粒子ほど空気分子や熱放射との衝突で簡単に量子状態が壊れてしまうため真空や低温など完璧に近い隔離環境が必要です。
このようにハードルは非常に高いのですが、「もし数千個の原子からなるナノ粒子でも量子的な干渉が起きると証明できたら?」という問いかけは、量子力学の根本に迫る挑戦です。
そこで今回研究者たちは「原子7000個から成る金属粒子にも量子の猫は宿るのか?」を検証することにしました。
本当にそんな巨大粒子全体が、自ら波となって明確な干渉縞を描くことなどできるのでしょうか?
原子7000個の粒子が描いた量子性
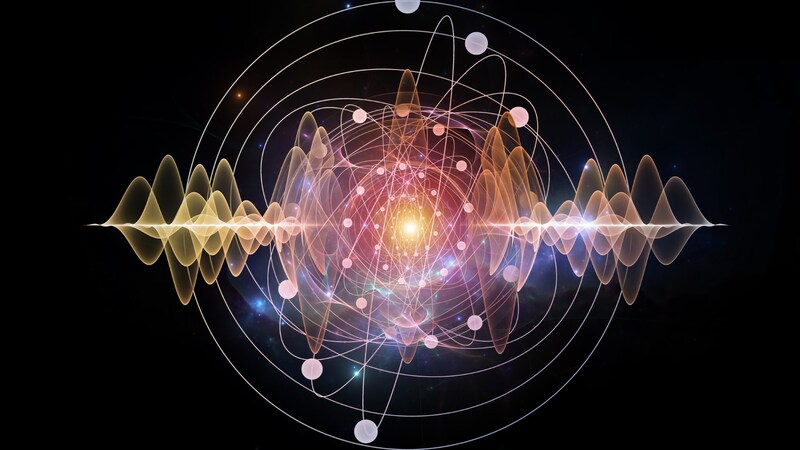
結論から言うと、7000個の原子からなる金属粒子でも波として振る舞うことが判明しました。
干渉計の最後に配置した検出器を横方向に走査すると、粒子が通過した位置に強弱のある縞模様が現れました。
これはクラスター粒子が同時に複数の経路を通ったことを意味し、量子力学が予測する自己干渉パターンそのものでした。
研究チームは理論モデルによる予測と比較することで、この干渉縞が量子論を前提としない古典的なモデルとは区別できることを突き止めました。
一方で、実験データは量子力学のモデルで非常によく再現されており、重ね合わせ状態を壊す要因(装置のずれや振動、粒子の熱運動など)も考慮すると量子論のモデルで良好に再現されました。
このとき、理論曲線には「0.78」という調整用の係数をかけて一致度を高めています。
要するに、金属粒子の位置は“波”として広がり、軌道を一意に割り当てられない状態でした。
この結果は何を意味しているのでしょうか?
端的に言えば、数千個もの原子からなる“塊”であっても自然は量子の原理をすぐには放棄しないということです。
私たちの直感に反して、金属のナノ粒子は「ここ」と「あそこ」を同時に進む不思議な状態、すなわちミクロな世界でしか成り立たないと思われていた原理が、より巨視的な領域にも生きていることが示されたのです。
研究チームは、この“猫的”量子状態の巨視性(マクロスコピシティ)を定量評価しています。
「マクロスコピシティμ」は、“どれだけデカい(長い・重い)世界まで量子らしさが食い込めているか”を数字1つで表す物差しです。
過去の実験では、より低い巨視性(μ=14.1)の値が記録されていましたが、今回の実験で得られた巨視性はμ=15.5であり、記録を更新したことになります。
この数値は対数表記なので、量子性の堅牢さは実際には1ケタぶん拡大したことになります。
過去にはより巨大な物体を重ね合わせにしたとする研究報告があり、それはそれで正しいのですが、実はそれらのケースでは同時に存在したとされる距離が非常に近かったり、保持時間が短かったり、物体の特定の性質(自由度)だけを量子的状態にしたものであったりと、制限がありました。
しかし今回の研究では、7000個の原子からなる金属粒子全体が、かなり離れた場所に同時に存在していた(波が広がっていた)ことが示されています。
距離、時間、全体か性質の一部かという総合的な面において、今回の研究成果は飛び抜けていると言えるでしょう。
さらに補足データも、この結果を強く裏付けています。
例えば質量40万~100万ダルトンという、より大きなクラスター粒子でも試験的に干渉計を通しています。
その際、干渉縞のコントラスト自体はむしろ質量が大きい粒子の方が高くなる傾向すら見られました。
一見不思議ですが、これは粒子が大きいほど光格子でより強く選別され、干渉に寄与する“粒子の揃い具合”が向上するためと考えられています。
ただし現行の設定では、100万ダルトン級の粒子になると量子モデルと古典モデルの予測がほぼ一致してしまい、干渉縞の有無だけでは「量子か古典か」を判別できなくなるとも報告されています。
裏を返せば、今後さらなる低速化や改良によっては、その100万ダルトン級の粒子でも量子的振る舞いを明確に実証できる可能性があるということです。